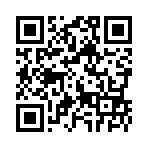決して趣味ではありません!!屋根塗り再び・・・
2011年08月24日
道具が増えすぎて手狭になった作業スペースを広げる為、
禁断の聖地(ウッドデッキ)に屋根を作っています。
我が家には結構広めのウッドデッキがあるのですが、
(4mx5m)
全く使わないので作業場を作りたいと思っていましたが、
中々建築許可が下りず(嫁の)
作品を置くギャラリーにすると言う事でようやくOK
骨組みだけは知人に激安で組んでもらい、
外装は自分でコツコツ作っています。
今日は屋根の下地を貼って、防水塗装2度塗り終了まで。
明日もう一度重ね塗りし、防水シート、ガルバニュームを張る予定です。
雨どいも付けなきゃ。
昨年の11月に自宅の屋根塗りした時には、
あまりのキツサに「2度とヤラン!!」と思っていたのに。
のど元過ぎれば・・・・と言うやつですね(笑)

禁断の聖地(ウッドデッキ)に屋根を作っています。
我が家には結構広めのウッドデッキがあるのですが、
(4mx5m)
全く使わないので作業場を作りたいと思っていましたが、
中々建築許可が下りず(嫁の)
作品を置くギャラリーにすると言う事でようやくOK
骨組みだけは知人に激安で組んでもらい、
外装は自分でコツコツ作っています。
今日は屋根の下地を貼って、防水塗装2度塗り終了まで。
明日もう一度重ね塗りし、防水シート、ガルバニュームを張る予定です。
雨どいも付けなきゃ。
昨年の11月に自宅の屋根塗りした時には、
あまりのキツサに「2度とヤラン!!」と思っていたのに。
のど元過ぎれば・・・・と言うやつですね(笑)

試行錯誤してます(昭和レトロ家具)
2011年08月24日
昭和レトロな家具を作りたくって、試行錯誤してます。
とりあえず、
昭和で
和風で
レトロ家具・・・
と言えば
ベニア板?
手垢とこびりついたホコリ?
黒ずんだアメ色・・・

と言うわけで、オールベニア板。
錆びあがったマイナスの木ネジが入手出来なかったので、全て釘!!
塗装は「柿渋!!」
一度塗って乾燥させたけど・・・・
透明で色が付かない(涙)
それもそのはず!柿渋染めは長い時間をかけて、
いい色になって行くと言うか、味が出てくるそうです。
でもそんなには待てません!!
次回イベントに持って行きたいので、
直ちに変色してもらわなければなりません。
そこで変色のメカニズムを調べてみました。
「柿渋に含まれるタンニンが紫外線や酸素に よって酸化され、
褐色or黒褐色に変色して行く」だそうです。

とりあえず、熱風を当てて酸化を加速させてみました。
結構良い色合いになりましたが、
出来れば黒褐色になってもらいたいかな。
欲を言えば、ベニアの表面が剥げたり、
少しヨレッと変形すると雰囲気が出るのだけど・・・・
温泉にでも漬けようかな。
温泉に入れて、サウナで乾かし、日サロで焼いて・・・
「柿渋」だけに「渋~い」
変な場面(え)を想像してしまいました(笑)

サイズはA4ピッタリサイズ!
棚板は溝切りなので、取り外し可能!
機能、構造はしっかり作っています。
まぁ許せる程度には、雰囲気も出ていると思うので、
あとは引き取って頂ける嫁入り先で年月を重ね、
柿渋効果で変色して行くのを楽しんでもらいたいと思います。
ちなみに、仕上げを変えてフレンチカントリーや、
ナチュラル系も製作しようと思います。
--以下wikiペディアより引用--
(長文なので興味の無い方はキツイかも)
柿渋(かきしぶ)は、渋柿の未熟な果実を粉砕、圧搾して得られた汁液を発酵・熟成させて得られる、赤褐色で半透明の液体。柿タンニンを多量に含み、平安時代より様々な用途に用いられて来た日本固有の材料である。発酵によって生じた酢酸や酪酸等を原因とする悪臭を有するが、20世紀末には新しい製法により精製され、悪臭が完全に取り除かれた無臭柿渋も誕生している。
歴史
文献で最初に記載されているのは10世紀頃であり、漆の下塗りに使用された記録が残っている。また、衣類に使用したのは、平安時代の下級の侍が着ていた「柿衣」(柿渋色は時に桧皮色とも混同され桧皮着:ひわだぎとも呼ばれた)がその始まりとされる。また民間薬として、火傷や霜焼、血圧降下や解毒などに効くとして盛んに利用された。
製法
原料となるカキの果実は柿タンニンの多い品種を用いる。未熟なカキの果実は甘柿でも渋柿でも渋を多く含むが、原料として用いられる渋含有量の多い果実は、通常渋柿品種のものである。まだ青い未熟果を収穫し、突き臼や粉砕機で砕き、樽の中に貯蔵して2昼夜ほど発酵させる。これを圧搾して「生渋」を得る。生渋を静置して上澄みを採取したものを「一番渋」と呼ぶ。また、生渋を搾ったときの絞りかすにはまだ多くの渋成分が残っているため、これに水を加えてさらに発酵させ、圧搾して得られたものを「二番渋」と呼ぶ。これらの液体を数年間保存して熟成させた後、使用することが多い。
用途
カキタンニンには防腐作用があるため、即身仏(ミイラ)に塗布したり、水中で用いる魚網や釣り糸の防腐と、強度を増すために古くから用いられてきた。また、木工品や木材建築の塗装の下地塗りにも用いる。縄灰と混ぜて外壁の塗装にも使用された。更に紙に塗って乾燥させると硬く頑丈になり防水機能も有するようになるため、かつてはうちわや傘、紙衣の材料として用いられ[1]、現在でも染色の型紙などの紙工芸の素材としても重要である。
タンニンが水溶性タンパク質と結合して沈殿を生じる性質は清酒の清澄剤として利用されており、今日ではこの用途で最も多く用いられている。塗料としての用途は近年は利用が少なくなっているが、シックハウス症状を起こさない塗料として再評価されつつある。染色にも用いられ、出来上がりの茶色の色合いが柿渋染めとして好まれる。
また、この柿渋染めの柿衣は上記術のように時に桧皮色とも混同され桧皮着(ひわだぎ)とも呼ばれ、その除菌効果のある布地を利用して山野の汚染の少ない良質な河川や井戸の水を漉して飲用にも利用した。
あさイチ(NHK総合テレビジョン,2010年09月27日)によれば、島本整(広島大学大学院生物圏科学研究科・食品衛生学研究室)の研究成果によって、ノロウイルスなどに抗菌作用が認められる[2]とされ、柿渋の除菌スプレーなどの応用製品が販売されている。
とりあえず、
昭和で
和風で
レトロ家具・・・
と言えば
ベニア板?
手垢とこびりついたホコリ?
黒ずんだアメ色・・・

と言うわけで、オールベニア板。
錆びあがったマイナスの木ネジが入手出来なかったので、全て釘!!
塗装は「柿渋!!」
一度塗って乾燥させたけど・・・・
透明で色が付かない(涙)
それもそのはず!柿渋染めは長い時間をかけて、
いい色になって行くと言うか、味が出てくるそうです。
でもそんなには待てません!!
次回イベントに持って行きたいので、
直ちに変色してもらわなければなりません。
そこで変色のメカニズムを調べてみました。
「柿渋に含まれるタンニンが紫外線や酸素に よって酸化され、
褐色or黒褐色に変色して行く」だそうです。

とりあえず、熱風を当てて酸化を加速させてみました。
結構良い色合いになりましたが、
出来れば黒褐色になってもらいたいかな。
欲を言えば、ベニアの表面が剥げたり、
少しヨレッと変形すると雰囲気が出るのだけど・・・・
温泉にでも漬けようかな。
温泉に入れて、サウナで乾かし、日サロで焼いて・・・
「柿渋」だけに「渋~い」
変な場面(え)を想像してしまいました(笑)

サイズはA4ピッタリサイズ!
棚板は溝切りなので、取り外し可能!
機能、構造はしっかり作っています。
まぁ許せる程度には、雰囲気も出ていると思うので、
あとは引き取って頂ける嫁入り先で年月を重ね、
柿渋効果で変色して行くのを楽しんでもらいたいと思います。
ちなみに、仕上げを変えてフレンチカントリーや、
ナチュラル系も製作しようと思います。
--以下wikiペディアより引用--
(長文なので興味の無い方はキツイかも)
柿渋(かきしぶ)は、渋柿の未熟な果実を粉砕、圧搾して得られた汁液を発酵・熟成させて得られる、赤褐色で半透明の液体。柿タンニンを多量に含み、平安時代より様々な用途に用いられて来た日本固有の材料である。発酵によって生じた酢酸や酪酸等を原因とする悪臭を有するが、20世紀末には新しい製法により精製され、悪臭が完全に取り除かれた無臭柿渋も誕生している。
歴史
文献で最初に記載されているのは10世紀頃であり、漆の下塗りに使用された記録が残っている。また、衣類に使用したのは、平安時代の下級の侍が着ていた「柿衣」(柿渋色は時に桧皮色とも混同され桧皮着:ひわだぎとも呼ばれた)がその始まりとされる。また民間薬として、火傷や霜焼、血圧降下や解毒などに効くとして盛んに利用された。
製法
原料となるカキの果実は柿タンニンの多い品種を用いる。未熟なカキの果実は甘柿でも渋柿でも渋を多く含むが、原料として用いられる渋含有量の多い果実は、通常渋柿品種のものである。まだ青い未熟果を収穫し、突き臼や粉砕機で砕き、樽の中に貯蔵して2昼夜ほど発酵させる。これを圧搾して「生渋」を得る。生渋を静置して上澄みを採取したものを「一番渋」と呼ぶ。また、生渋を搾ったときの絞りかすにはまだ多くの渋成分が残っているため、これに水を加えてさらに発酵させ、圧搾して得られたものを「二番渋」と呼ぶ。これらの液体を数年間保存して熟成させた後、使用することが多い。
用途
カキタンニンには防腐作用があるため、即身仏(ミイラ)に塗布したり、水中で用いる魚網や釣り糸の防腐と、強度を増すために古くから用いられてきた。また、木工品や木材建築の塗装の下地塗りにも用いる。縄灰と混ぜて外壁の塗装にも使用された。更に紙に塗って乾燥させると硬く頑丈になり防水機能も有するようになるため、かつてはうちわや傘、紙衣の材料として用いられ[1]、現在でも染色の型紙などの紙工芸の素材としても重要である。
タンニンが水溶性タンパク質と結合して沈殿を生じる性質は清酒の清澄剤として利用されており、今日ではこの用途で最も多く用いられている。塗料としての用途は近年は利用が少なくなっているが、シックハウス症状を起こさない塗料として再評価されつつある。染色にも用いられ、出来上がりの茶色の色合いが柿渋染めとして好まれる。
また、この柿渋染めの柿衣は上記術のように時に桧皮色とも混同され桧皮着(ひわだぎ)とも呼ばれ、その除菌効果のある布地を利用して山野の汚染の少ない良質な河川や井戸の水を漉して飲用にも利用した。
あさイチ(NHK総合テレビジョン,2010年09月27日)によれば、島本整(広島大学大学院生物圏科学研究科・食品衛生学研究室)の研究成果によって、ノロウイルスなどに抗菌作用が認められる[2]とされ、柿渋の除菌スプレーなどの応用製品が販売されている。